アーユルヴェーダは、インド発祥の伝統医学です。
起源にはいろいろな説がありますが、一般的には五千年∼数万年の歴史がある、といわれています。ギリシャ医学、チベット医学、中医学、そして仏教などにもアーユルヴェーダの影響を見ることができます。仏陀の主治医ジーヴァカはアーユルヴェーダ医でした。
「アーユスAyus」=生命、「ヴェーダVeda」=科学、という意味合いです。非常に科学的な理論ですが、それ以上に哲学でもあります。与えられた一生を健康に、幸せに、そして有益に送るための知恵が説かれています。
アーユルヴェーダは生命を体、精神、五感、魂の統合体としてみます。健康で有益な人生を送るためにはこの4つがバランスの取れた状態でいることが不可欠です。心身の病を患う方には回復の手助けを、すでに健康な方には健康と若さを保つ手助けを。自分自身と、自分を取り巻く環境の中でバランスを保ちつつ生きていく知恵を、アーユルヴェーダが教えてくれます。
アーユルヴェーダの基礎概念の一つに五元素理論があります。これは、宇宙に存在するすべてのもの(有機質、無機質を問わず)が五元素でできているというものです。つまり、空、風、火、水、土の元素があらゆるものを構成しているということです。これらが生命体の中ではヴァータ(空、風:「動きのエネルギー」)、ピッタ(火、水:「熱や変換のエネルギー」)、カファ(水、土:「組織の構成や保護的エネルギー」)という機能的エネルギー(ドーシャ)となって生命の活動を維持しています。また、ヴァータ、ピッタ、カファの先天的な割合により、ひとりひとりの体質や性格の傾向が概ね決まってきます。これら3つのドーシャは生命の維持に必要なエネルギーですが、割合のバランスが乱れると病気を引き起こします。
アーユルヴェーダは、病気の主な原因として、このドーシャバランスの乱れと、精神バランスの乱れを挙げています。治療は伝統的に製剤(薬草や鉱物などから作られる)、施術、デトックス、ヨガ、瞑想、食事・生活療法などを使い、ドーシャと精神のバランスをとっていくことが基本です。つまり、アーユルヴェーダは病気を治すのではなく、人を治していくといえます。

また日常生活を送るうえで、心身の良い状態を保つためのヒントも与えてくれています。食べ物(5つの感覚器から入ってくるものを全て食べ物とみなします)、思考、行動、習慣などはすべて、1.私たちの体と心を平穏にし、健康に近づけてくれるものと、2.私たちの体と心のバランスを乱し、健康を妨げるものにわけることができます。一時的に楽しいものやおいしいものが長期的にみて有益とは限りません。何が自分にとって本当によいものか、アーユルヴェーダは選択するときの基準を教えてくれます。
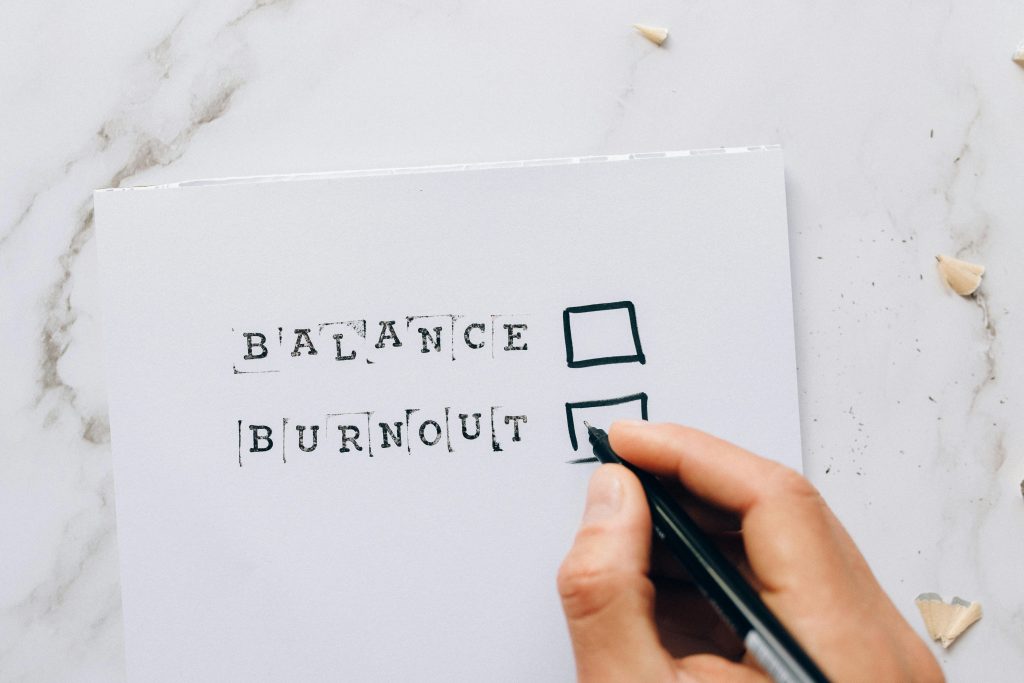
インドの古い時代から伝えられてきた伝統医学ですが、この智恵はどの時代に生きる人々にもよりよく生きていくためのマニュアルとなることでしょう。
よくある質問
Q. アーユルヴェーダは宗教ですか?
A. 宗教ではなく、論理的な科学・医学・哲学だといえます。人は体、精神、五感、魂の4つの統合でできているため、健康を得るためにはこの4つの面からアプローチしないといけません。特に精神性を高めるためにヨガや瞑想を勧めるため宗教と誤解されるのかもしれませんが、これらの精神への好影響は科学的にも証明されています。アーユルヴェーダはどの宗教にも属しませんし、信仰心を持つことは精神性を高めるのによいですが、特定の宗教を進めることは一切ありません。
Q. アーユルヴェーダは大昔にインドで生まれたものなので現代の日本人には当てはまらないのではないですか?
A. アーユルヴェーダは普遍的な法則を説いています。場所、時の流れは普遍的なものを変化させることはありません。また、アーユルヴェーダは厳格なルールの中に柔軟さをもっています。食事や慣習の違いなどは、基本的なルールさえ守っていればその国、時代に合わせて変化させていくことができます。大事なのは基本の概念とルールを守って、その中で柔軟に対応していくことです。